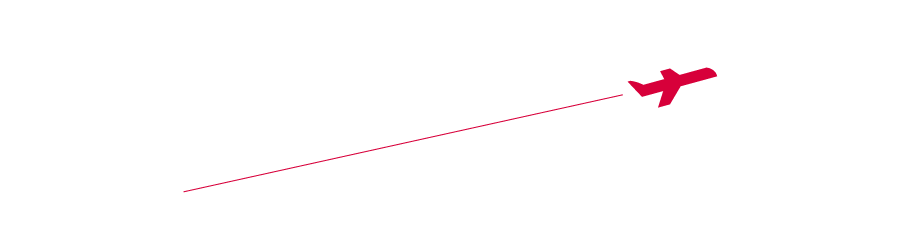神戸市会議員(神戸市北区選出)公式ウェブサイト
神戸市における「地域マネージメント(維持管理)」の「これまで」と「これから」

地域では、日々、さまざまな問題が起きます。誰かがなんとかしなければならない課題もたくさんあります。犯罪、電灯の故障・整備、ゴミ、公園の維持管理、空き家・空き地・路地・雑木林の管理、大きな荷物の運搬、ケガ人・病人の発見と救急通報、葬儀、自然災害対策、お祭りの準備・・・。「地域の課題」は多岐に渡ります。そして、そうした「地域の課題」は、地域の中での「暮らしやすさ」に直結するものです。こうした、地域の多様な課題に向きあい、地域をマネージメント(維持管理)していくための仕組み、それをサポートする行政の取り組みについて、「これまで」と「これから」の展望を、神戸市会議員・坊やすながが、インタビュー形式で語ります。
「これから」の時代の地域マネージメント(維持管理)のありかたを創造する ~ 一番の足元は「地域力」
―――神戸市における、いままでの「地域マネージメント(維持管理)」のありかた、というのはどのようなものだったのでしょうか。
(坊)神戸市に限らず、それぞれの地域には、古くから「自治会」などの自治組織があり、地域の課題解決や合意形成の場として機能してきました。しかしながら時代は変わり、社会環境も変化が進む中で、従来型の「自治会」の運営がしんどくなってきている状況があります。「自治会」を通じた活動に参加しようという人が減ってきているということです。その結果、現代においては、「地域の課題を自治会に集約し、自治会で議論して解決する」ということが実質的に難しくなってきています。例えば、地域の中に、「公園の一部を畑にして活用したい」と考える人たちがいたとして、その思いをすくいあげて、議論して、意志決定して、実行を応援していく力を現代の「自治会」が有しているかというと、現実的にはそうはなっていないでしょう。これでは、地域は活性化していきません。地域の課題を拾い上げ、解決の道筋を議論して合意形成して、実際に実行するためのお金と人を組織していく、そういう仕組みを作り直さなければ、地域の課題は放置され、荒廃が進むばかりです。「地域を良くするために、なんとかしたい」。そんなふうに考える人たちの思いをしっかりと受けとめていくための仕組みが必要です。
―――確かに、そうした仕組みがなければ、地域活性化など夢のまた夢でしょうし、それどころか、地域の中で日々発生する問題が解決されないまま放置され続け、「暮らしにくい地域」であり続けてしまうわけですね。それは大きな問題だと思いますが。
(坊)そうなんです。地域課題を解決する枠組みを作る、ということは、非常に重要度の高いテーマなのです。例を挙げて考えてみましょう。地域では、空き巣を始め、さまざまな犯罪が起きることがあります。こうした地域犯罪については、「犯罪が起きやすい地域」があると言います。それは、「犯罪をやりやすい地域」があるということと同義です。地域で暮らす人が、絶えず地域に目を配り、必要に応じて声掛けなどが積極的に行われる地域では、「犯罪が起きにくい」と言えるでしょう。共働きで両親が働いている間、地域では子どもが不審者に狙われてしまっているような環境では、とてもではないですが、共働きで働きながら、安心して子どもを育てていくことなどできません。安心して暮らすことのできる地域をつくることは、子育て対策にもつながるものです。「地域づくり」は、あらゆる課題解決の基礎となる大切な取り組みであると言えます。
―――なるほど。「地域づくり」は、他の様々な政策課題を解決していくための土台となる非常に重要な取り組みであるのですね。
(坊)はい。私は、一番の足元は「地域力」だと思っています。「地域力」が崩れてきているから、いろんな問題が次々と起きてきているのだと思っています。こうした「地域力」を、現代にあわせた、新しいかたちで再構築していくことが、今、最も、政治に求められていることだと考えています。その本質から目を背けて、「地域力」が弱っていることを原因として次から次に発生してしまう新しい問題に対して対処療法的に予算を付け続けていてもキリがありません。それでは本質的な課題解決につながりません。

―――では、「これから」の時代の地域のマネージメント(維持管理)のありかた、言い方を変えれば、地域で暮らしている中で日々発生する問題に対応していくための枠組みとしては、具体的に、どのようなものが考えられるのでしょうか。
(坊)神戸市の「子育て支援政策」の「これまで」と「これから」でもお話したように、行政や保育・医療の枠組みでは対応しきれないイレギュラーも含めて、地域の中で包括的に困りごとに対応してくれる「地域サポート会社」が必要だと考えています。
―――なるほど、地域の課題をケアしてくれる様々なサービスを提供してくれる「地域サポート会社」が中心となって、地域のマネージメント(維持管理)を進めていくモデルを作っていく、ということですね。
(坊)そうです。縦割りではなく、地域の課題に包括的に対応可能なパッケージ(枠組み)として、「地域サポート会社」の設立を促していくイメージです。この「地域サポート会社」は、地域の課題、例えば、既存の保育や医療の枠組みではカバーしきれない「子育てにおけるイレギュラー」のケアであるとか、高齢の方では困難な大きな荷物の運搬・設置・組み立てなどのサポート。それから不用品のリユース・廃品処理のサポート、草刈りやゴミ拾いをはじめとする地域の美化や、防犯・不審者対策としての見回り・声掛け、さらには、独居されている高齢の方々の巡回ケアなど、ありとあらゆる地域課題のためのケアサービスを包括的に提供する会社です。地域サポート会社のジャンパーを着た人が街を歩いていたら安心だね、と思えるような状況を作れたら理想です。こうした「地域サポート会社」は、地域の課題に包括的に対応していくための基礎的な枠組になりうるものです。こうした地域サポート会社を、行政サイドも、縦割りではなく、包括的に(予算もつけて)支援していくことが重要だと考えています。
―――なるほど、まず、ありとあらゆる地域の課題の受付窓口として「地域サポート会社」を配置して、地域の課題解決が進みやすい環境を整えていく、ということですね。その構想を実現していくにあたっての課題としては、どのようなものがありますか。
(坊)地域サポート会社に求められることは、やはり、「安心感」「信頼感」だと思います。地域で暮らす住民が、地域サポート会社のことを信頼できるようにしていかなければ、この仕組みはうまく回っていかないと思います。よく知らない、外部の資本が、お金儲けのためだけに運営している会社だと思われてしまっては、絶対にうまく回っていかなくなると考えます。その意味で、設立にあたっては地域の篤志家の方々に寄付をしていただいたり、住民自身が株主になって経営に参画できる仕組みを整えたり、中心メンバーには神戸市役所や区役所のOBを起用したりして、「信頼できる」地域サポート会社となるようにしていかなくてはなりません。その旗振りが、政治家や行政(市役所)に求められることだと思っています。地域で人望のある人物にリーダーとして立ってもらえるよう働きかけていくことも政治家として重要な仕事であると思っています。
―――地域の人間、つまり民間主導で地域サービス会社を設立・運営していく、となりますと、「そうした地域課題のケアは、行政(市役所・区役所)の仕事なのではないか?税金も納めているのだから、本来は、その範囲で、行政(市役所・区役所)から行政サービスとして無償で提供されるべきものなのではないか?なぜ、地域サポート会社にサービス料を払って地域の課題解決をしてもらわないといけないのだ?という意見も出てきそうですが。
(坊)そうしたご意見も当然出てくることでしょう。しかしながら、地域の課題解決の他にも、行政として対応すべき課題が山積みである状況の中で、すべてのことに、行政として予算を振り当てて対応をしていくわけにはいきません。そして何より、ただ単に予算を注いで行政サービスとして提供していくばかりでは、いつまで経っても持続可能な(サステナブルな)仕組みとならないわけです。かえって、税負担を通じて、住民の方々の負担を高めてしまうことにもつながりかねません。それよりも、「地域のことは地域でなんとかする」、そうした仕組みを整備して運用していこうとする「地域の努力」を、行政としてサポートしていくことが重要だと考えます。そして、しっかりと経済が好循環するような仕組みを作りだしていくことで、持続可能な(サステナブルな)地域サポートの仕組みができあがるのだと信じています。マンションの管理組合と同じです。自分達の困っていることは自分達が一番わかっているわけですし、一番気持ちをこめて動けるわけです。ちゃんとした管理組合があるマンションが何年経っても美しさを維持しているのと同じです。まず、自分達で、ちゃんとする。そして、ちゃんと自分達でしよう、と思っている人たちを、行政・政治がちゃんと応援する。そういうことだと思っています。
―――なるほど、「地域サポート会社」とすることで、地域の中に、経済の好循環を創り出して、持続可能な(サステナブルな)地域を創り出していく、ということですね。
(坊)そういうことです。地域サポート会社が機能するようになれば、これは、地域における雇用の受け皿にもなります。シルバー人材、シニア世代の新たな活躍の場としても期待できるものです。そして、地域サポート会社では、ぜひ、地域に暮らす、さまざまな個性をもった人材に副業やリモートで働いてほしいと思っています。そうすることで、地域内交流にもつながると思っています。例えば、地域サポート会社のホームページを、地域で暮らしながら働いているフリーランスのWebデザイナーに開発・運用してもらったりすることで、日頃接点のない人たちの間に、新しい交流が生まれていくわけです。そして、地域のサポート会社に支払われるサービス料は、こうした、地域に暮らしながら働いている人たちに給与・報酬として支払われていくわけです。そうして、地域で経済が循環していくわけです。これが、これからの時代にふさわしい、新しい形の地域マネージメントのモデルになっていくと信じています。