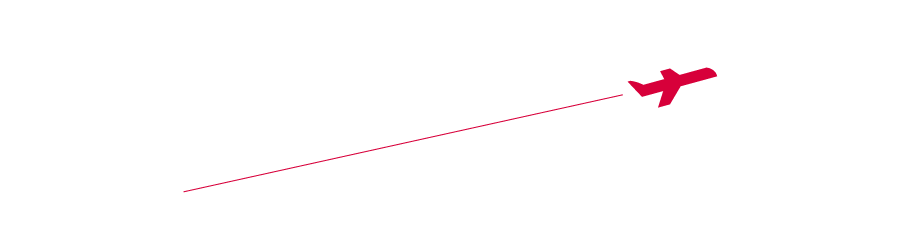神戸市会議員(神戸市北区選出)公式ウェブサイト
神戸市における「街並み・まちづくり」の「これまで」と「これから」
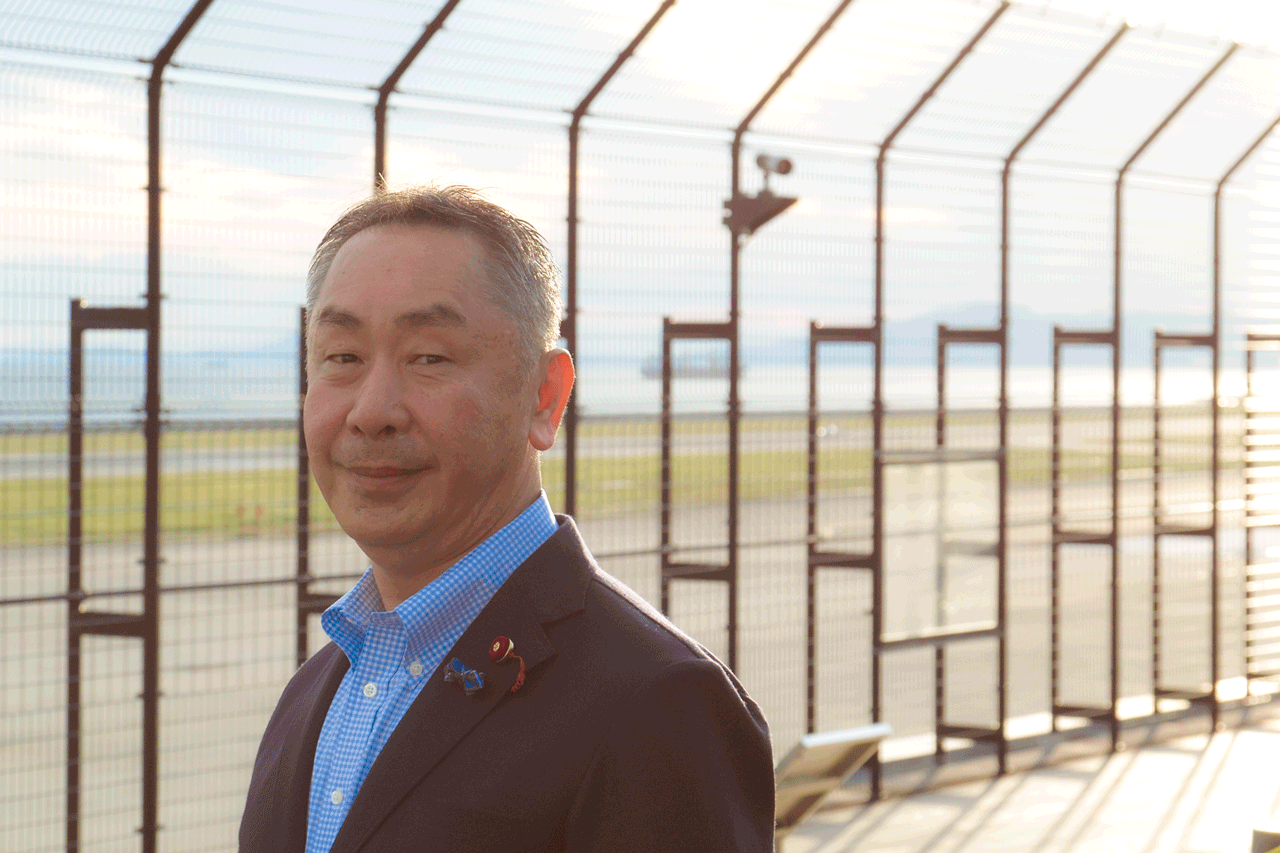
神戸の「街並み・まちづくり」のこれからについて、神戸市会議員・坊やすながが、インタビュー形式で語ります。
まとめ ~坊やすながが考える神戸の街の「これから」~
■ 人口減少時代の新しいまちづくりの手法として、既存の街の「リブランディング」を進めていく(今まで築き上げてきた街のブランドの上に、新しいイメージを重ねて、ブランドを強化していく)
■ 具体的には、街中に、緑を増やし、皆が癒やされるような、「ヒーリング・ガーデン都市」を目指していく
■ まず、その象徴的な取り組みとして、三宮の海側にある磯上公園のリニューアルを働きかけ、実現させた
■ これにより好循環が生まれ、磯上公園の周辺数ブロックに渡り、近隣で暮らし・働く人達が自発的に都市空間を「ヒーリング・ガーデン」的なものに拡張させていってくれるのではないかと期待している
■ 今後、このイメージを神戸市全体に広げていくために、まずはなんといっても、神戸の空の玄関口である神戸空港周辺、それからポートアイランドを「ガーデン都市」に変えていくことが重要だと考えている
■ そうして徐々に、神戸市の伝統的なブランドイメージに「ヒーリングガーデン都市」としてのブランドイメージを次々と重ねあわせていくことで、現代そして未来に通用する<都市としての魅力>を再構築していくことができると考えている
「リブランディング」によって、神戸を、世界を魅了する「ヒーリングガーデン都市」へ
―――神戸市における、「これから」のまちづくりのありかたというのは、どのようなものになっていくべきだとお考えですか。「これまで」を踏まえて、お話をお聞かせください。
(坊)神戸の街は、昔からブランド力があり、全国的・世界的に、「いい街」として認識されてきました。しかし、阪神・淡路大震災があり、復旧・復興事業を優先したことから、大阪や京都のように主要駅周辺での大規模な開発ができずに30年が経ちました。時代に合わせて、街に手を入れて、街を変えていく時がやってきました。一昔前と同じような手法ではなく、時代に合った新しい手法で、まちづくりを進めていくべき時がやってきました。かつて、人口が大きく増加していた局面においては、神戸市は積極的に開発を行ってきました。しかし、現代は違います。人口が減少していく局面にあるわけです。かつてのように、積極的に開発を進めていく時代ではありません。
―――山を切り拓いてニュータウンを作ったり、海を埋め立てたり、街中にどんどん新しいビルを建てたりすることで「まちづくり」を進めていく時代ではなくなった、ということでしょうか。
(坊)新しくビルを建てたりビルを建て替えたりするのは大変です。とんでもない額のお金がかかります。もちろん、(老朽化が進行しているビルなど)建て替えが不可避なものについてはやらなければならないですが、現実的には、全部のビルを建て替えるわけにはいきません。ですが、街の雰囲気を変えることは、少ない予算でも実現できることです。今まで築き上げてきた街の上に、新しいイメージを乗せていくわけです。人口減少時代の新しいまちづくりの手法と言えるのではないでしょうか。街のイメージを変え、ブランドを創りあげていくことができれば、「暮らしたい」と思う人も増えていきますし、自然と地価も上がっていくことでしょう。どんどん好回転が生まれていきます。政治・行政が流れさえ作れば、あとはどんどん自然に成長していくわけです。その最初の流れを生み出すのが政治の仕事だと思っています。
―――具体的には、神戸を、どうやって、どのようなイメージを持った街に変えていくことが考えられるのでしょうか。
(坊)神戸という街は、「ガーデン都市」としてのブランドを築いていくことができると思っています。街なかに緑が多く、人たちがいやされる、言うなれば「ヒーリング・ガーデン都市」を目指していくのが良いのではないかと思っています。道への植樹や、ボタニカル空間(植物に囲まれたくつろぎのエリア)の整備、ビルの屋上緑化。神戸は、これからますます、緑に満ちた都市空間へと変化していきます。しかし、まちに緑を増やすことはとても大切なことですが、ただ単に緑が増えればよいというものでもありません。重要なことは、本当の意味で良い「空間」を作るにあたっては「哲学」が必要だ、ということです。哲学がないものは、長続きしません。ただ単に「きれいだね」ということだけでは、人の心に響きません。一度見たら、その瞬間だけ満足して、それでおしまいです。そのようなものは、長続きしませんし、そうしたものを求めて人がやってくるとしても、一時的な現象で終わってしまいます。
―――2024年6月、三宮の海側にある磯上公園がリニューアルされました。日本庭園が整備され、一般に開放されているのが印象的です。ただ単に「緑を増やす」ということにとどまらない哲学を感じます。
(坊)そうですね。磯上公園は、現代にふさわしい新しい形の日本庭園が園内に整備され、「ヒーリングガーデン」として生まれ変わりました。「現代にふさわしい新しい形の日本庭園」とはどういうことか、少しお話をさせていただきたいと思います。日本庭園というのは、五感が開かれる空間です。「目で聴き、耳で見る」ことができる空間です。そうして、無心になれる空間です。虚心坦懐、庭で心を澄ましているうちに、まるで自分と自然が一体になっているかのように感じられるわけです。「みな、ひとつの自然として生きている」。そうした「仏心(ぶっしん)」を育むことのできる空間です。日本庭園には、哲学があるのです。しかし、日本庭園というのは、かつては、一部の権力者のためだけのものでした。お金があり、権力がある人が、それを誇示するために立派な庭園を作り、自らにおもねる人だけをその空間に招きいれる、というような、いわば閉ざされた空間でした。そうではなく、誰しもが恩恵を得られ、効用を得られるように、「公に開かれた日本庭園」として作られたのが、磯上公園に作られた日本庭園なのです。ここには哲学があります。誰しもが、公園で休み、心を洗うことができるのです。心がしんどくなったときに癒やされる場所、それがヒーリングガーデンです。現代における「鎮守の森(ちんじゅのもり)」といってもよいでしょう。このような哲学をもった空間であればこそ、人が、集まってくるのだと思います。一過性のものではなく、人が通い、人が集い、未来に渡って持続する空間となっていくでしょう。

磯上公園ヒーリングガーデン
(神戸市中央区八幡通)

磯上公園ヒーリングガーデン
(神戸市中央区八幡通)
―――いいですね!そうした空間が、磯上公園からはじまって、神戸中、日本中、世界中に広がっていくとよいな、と思います。
(坊)そうですね。新しくなった磯上公園は、ある意味で、象徴的な空間です。その延長線に、まち全体の発展があるのだと考えます。新しくなった磯上公園の中に作られた日本庭園のことを「よいな」と感じた人たちが、その周辺、そして、町のあちこちで、自分たち自身で同じ哲学をもった空間を創り出していく。そうした好循環が生まれていけば、町全体が、ヒーリングガーデンになっていきます。人は、本心から「いい!」と思ったものには、自発的に、時間とお金と労力を注いでいくものなのです。ですから、政治・行政は、ビジョンを示すことが大切だと思っているのです。「こういうの、いいですよね?」と、具体的に示す。そこに共感の輪が広がっていけば、あとは、民間が、自然と、まちを作り広げていくのです。
―――そうした流れが生まれたら素敵ですね。神戸の中心・三宮周辺以外についても、そうした好循環を生み出していくためのシンボル、きっかけがあるとよいように思いますが、どうでしょうか。
(坊)なんといっても、やはりまずは、神戸空港周辺、それからポートアイランドを「ガーデン都市」に変えていくことが重要だと思っています。海外から来たお客様が、飛行機から降りて、荷物を持って外へ出た時に見て感じたイメージが、神戸のイメージになるわけですよね。だから、まずは、そこをしっかり「ガーデン都市」に変えていかなくてはならない。そうすることで、神戸に着いた瞬間に、「あっ!神戸に来たな!神戸、いいな!」って感じてもらえるようになるんだと思うのです。それが、神戸の新しいイメージになり、新しいブランドになる。その「神戸、いいな!」っていうのは感覚的なものなんですよね。「なんかよくわからないけれど、なんかいい!」というようなものなのです。街全体にあふれる雰囲気、空気のようなものです。今までの世の中は、そうした「感覚的なもの」を軽視しすぎてきたように思います。しかし、時代は、そうした「感覚的なもの」を必要としていて、求めているのだと思います。これからのまちづくりは、そうした「神戸って、なんかいいな、来ると癒やされて、満たされるな」という感覚、空気を作っていくことだろう、と考えています。
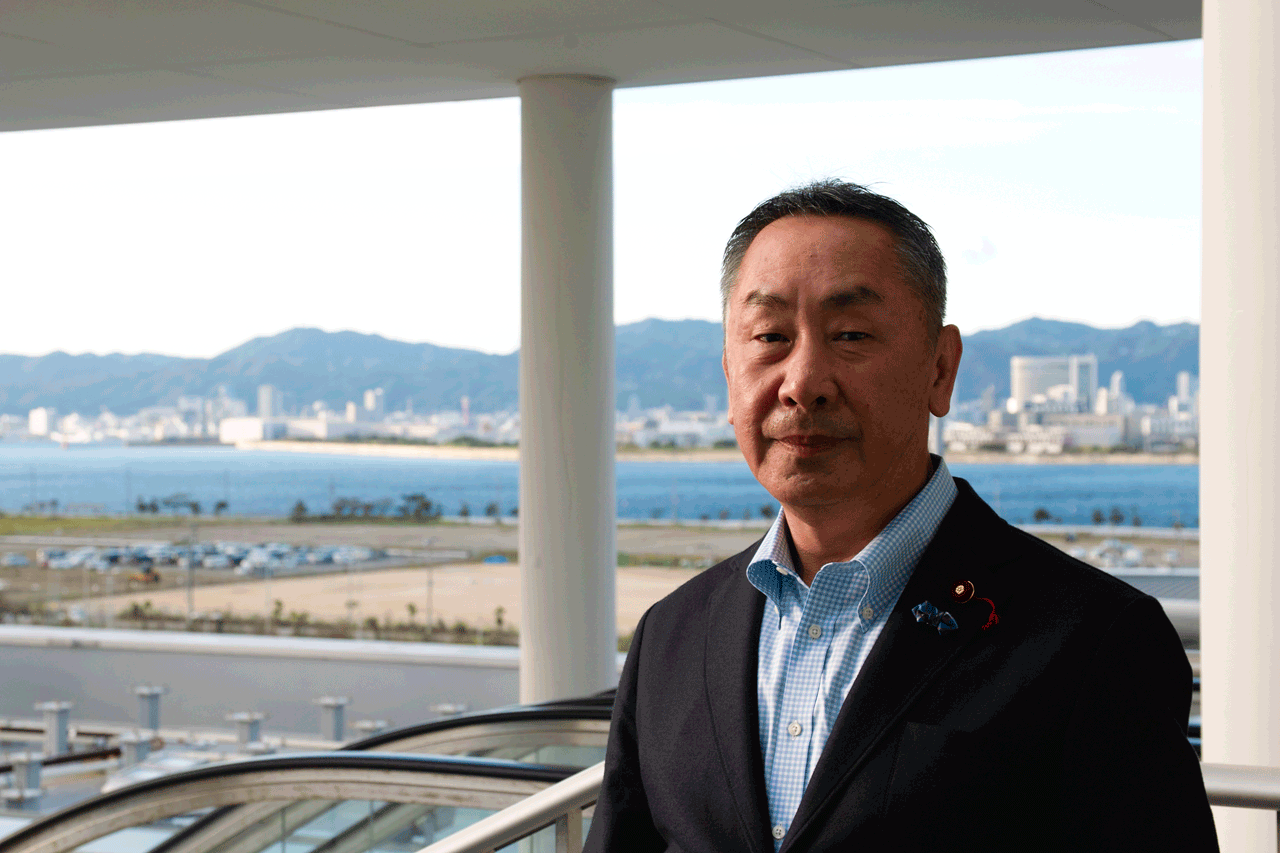
神戸空港
―――「まちづくり」=ハードウェア・インフラの整備だけではないのですね。癒やされて、心豊かになるまちをつくる、ということは、いわゆる都市政策だけではなくて、他の政策分野にもかかわってくる、横断的で、核心的なテーマであるように思えます。
(坊)ヒーリング、癒やし、調和、和を以て貴しとなす、そうした考え方がこれからの時代においては重要だよね、と皆が思うようになれば、都市政策だけではなくて、福祉政策をはじめとするその他の分野の政策においても、すべてにおいて、一本の筋が通っていくんです。そうして、新しい価値観が確立していくんだと思うのです。そうした価値観が、神戸から生まれ、日本という国全体に広がっていって、日本が、新しい経済のリーダーとして、世界を調和させていく。そうした未来を作れたらいいな、と思いませんか? 現代の経済は、互いを潰し合い、奪い合い、勝つか負けるかで競い合う経済です。そうではなく、これからの経済は、互いを活かしあい、癒やしあい、和をもって生きていくことが貴しとされる経済であるべきだと思います。あのまちにいけばこんな癒しがある。いや、あのまちにいけばこんな癒しがある。日本中、世界中で、さまざまな癒しのかたちが生まれ、それぞれの癒しをアピールしあうような、良い意味での「競争」が生まれていけば、どんなにかよい世の中になるでしょうか。

東遊園地
―――一方で、三宮から30分ほど車を走らせると、田畑や森林が広がる北区の「里山」にたどり着きます。この都市と里山の近さも神戸の魅力です。人々はどのように向き合うべきと思いますか。
(坊)自然が豊かな「里山」は神戸の財産だと考えています。先人たちが守ってきて我々が引き継いでいるので、将来の人たちにしっかりバトンを渡さなければなりません。いま「森の未来都市 神戸」と呼ばれる、時代の変化で人が管理しなくなった里山の林を適切に伐採して資源として活用しながら、森を若返らせることで森林を守ろうという施策も立ち上がりました。これも「里山」を未来に引き継いでいくための一つの方法になるのだと思います。
さらにいうと、森が若返ることで農村での人々の暮らしも充実していくと思います。そうなると、神戸での住まい方の新しい価値が生まれていき、きっと神戸のブランド力の強化につながっていくのではないでしょうか。