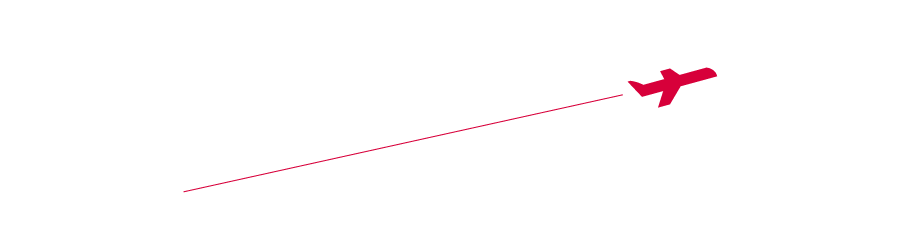神戸市会議員(神戸市北区選出)公式ウェブサイト
神戸市北区「道の駅 フルーツフラワーパーク大沢」の「これまで」と「これから」

「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」が誕生するまでの歴史、そして、これからの展望を、神戸市会議員・坊やすながが、インタビュー形式で語ります。
勉強会を積み重ねて誕生した、新しい「道の駅」
―――六甲北有料道路・大沢ICおりてすぐのところにある「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」には、サーカステントを思わせる白い3つの小屋「FARM CIRCUS」の中に、地元の農家さんが毎日届けてくれる採れたての野菜や果物の直売所に加え、地元の産品をふんだんに使った料理を楽しむことのできるカフェや食堂・レストランもあり、神戸の豊かな自然の恵みを満喫することができます。加えて、遊園地をはじめとするさまざまな施設もあって、一日ゆったり過ごすことのできる貴重な場所になっていますね。この「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」は、いつごろどのようにして誕生したのでしょうか。
(坊)前身となる「神戸フルーツ・フラワーパーク」は、もともと、バブル期の1993年に、神戸市立の施設として作られたものです。オープン当初こそ賑わいましたが、その後は厳しい状況となり、維持が大変な状況となっていました。「なんとかしなければならない」と考え、政治家としてリーダーシップを発揮して、「あるべき姿」について広く議論を重ねてきました。そうして、2017年に「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」として生まれ変わったのが現在の姿なのです。
―――なるほど、もともとバブル期に作られたものを、時代にあわせて、2017年に新しく「道の駅」にリニューアルされたのですね。結果として、「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」は大変賑わっていますが、リニューアルにおいて大事にした点はどういった点だったのでしょうか。
(坊)「普通にやったのでは、うまくいかない」と考えました。やはり、地域の皆さんが主体となって、思いをもって運営していかなければ、いい形にならないだろう、と考えたのです。お金の話でも、仮に運営を、神戸市の外にある運営会社に委託してしまうのであれば、せっかく利益が出るようになっても、利益も神戸市の外に流れていってしまいます。やはり、やるからには、神戸市の中の人達、特に、地域の人達が中心となって運営する形を作っていかなくてはならない、と考えました。そこで、私自身リーダーシップを発揮して、あるべき姿を議論するための「勉強会」を重ねていったのです。その結果、地元の事業者で構成される「北神地域振興」が、コンペに参加して、運営事業者として選定されることになったのです。こうした積み重ねを経て、いまのような、地域の皆さんにも、地域の外からいらっしゃる皆さんにも愛される、「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」ができあがりました。

みんながハッピーになる、新しい「道の駅」
―――神戸市の中、地域の人達が主体的に運営する形を作り上げたことで、今のような愛される場所になっていった、ということなのですね。
(坊)そういうことだと考えています。生まれ変わった「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」は、再び賑わう場所となりました。近隣の商業施設3つ(イオンモール神戸北、神戸三田プレミアムアウトレット、道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢)合計で、年間700万人ほどの人が訪れる場所になっています。なんといっても、すぐ近くに有馬温泉もありますからね。買い物のあとは、温泉で疲れをとって帰ることもできるわけです。日帰りや一泊で行ける身近な観光スポットとしては最高なんじゃないでしょうか。
―――確かに、日本中、広く見渡しても、こんな素敵な観光スポットはありませんものね。 「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢がある」ということは、日本中の皆さんにとってもハッピーなことですね。 「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」にリニューアルされたことで、地域の皆さんにとってはどのような変化があったのでしょうか?
(坊)なんといっても、地域の人にとっては、住むエリアとしての価値が高まりましたよね。すぐ近くにある「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」に、毎朝、とれたての新鮮なお野菜や果物が集まってくるんですから!こんなにいい食材を、毎日気軽に購入できる場所が近くにあるエリアなんて、なかなかありませんよ。しかも、地産地消ですから、作り手も、すぐ近くにいるわけです。その気になれば、畑に行って、作り手の姿を見ることだってできるんです。「住みたい街」としての価値がどんどん高まっていると思います。ぜひ、このエリアに移住して、暮らしてみていただきたいですね。
―――地産地消、つまり、(農産物の)作り手が近くにいてくれている、というのは、確かに、地域に暮らす人たちにとっても、魅力的なことですね!それでは、農業に従事されている方たちにとっては、どのような変化があったのでしょうか?
(坊)農家さんにとっても、嬉しい状況となりましたよね。「直販」ですから、安く売らなくていいんですから。「いいもの」が、ちゃんとした値段で、ちゃんと売れる場所ができたわけです。利益もちゃんと受け取れます。
―――たしかに、自分たちで値段を決めて自分たちで売る「直販」であれば、きちんとした利益を確保できそうです。持続可能な農業の実現につながりますね。農業を営んでおられる方以外の事業者さんや、働く人達にとっては、どのような変化があったのでしょうか?
(坊)まず、この「道の駅」の事業を通じて生まれる利益が、神戸市の外に出ていかず、お金が地域をめぐっていくことになりました。雇用も生まれました。「道の駅」を通じて、地域の経済全体に、広くお金が循環していく「いい回転」が生まれたのではないかと思っています。
―――すごいですね。地元の人、農業をされておられる方だけでなく、あらゆる方面においてメリットがある形になっているのですね。
(坊)そうなんです。みんながハッピーなんです。「いい回転」が生まれている、ということです。こうした、関わる人みんなが「ハッピーだ」と思えるような絵(ビジョン)を描く。そして、そうした絵(ビジョン)を実際に形にして、皆さんが、自由に、思う存分、生き生きと活動できるような「環境をつくる」のが政治家の仕事だと思っています。

農業振興を軸に、広く商業の活性化につながる「道の駅」
―――それでは、そんな「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」をめぐる今後の展望をお聞かせください。
(坊)一番の目的はやはり「農業振興」なので、これからも「良いもの」を「良さに見合った値段」で、しっかりと売っていけるような状況を作っていくことが重要です。こうした場所(「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」)ができたことで、農業をやりたい人、特に「良いもの」を作ろうという意志と能力をもった人が、この地に移ってきてくれたらいい、と思っています。「ここでなら、売れるから、この場所で、農業をやろう」。そう思ってもらえるような環境を作り続けていきたいと思います。
―――「良いもの」を作ろうという思いを持った人たちが移ってきてくれるようになれば、ますます活性化していきますね。
(坊)そうですね。実際には、今、「使われていない農地」もたくさんあるわけですが、「農業をやりたい」という人が来ても、昔から土地を守ってきた地主からすると、簡単には貸せないわけです。大切な土地ですから。でも、「良いもの」を作ろうという能力と意志(志)のある人が「道の駅」に来てくれて、互いに信頼を築くことができるようになれば、農地を貸していくこともできるようになっていくでしょう。たとえば、高品質なイチゴを作ることができる人に農地の一部を貸していく、というように。そうして、成功事例、モデルケースがどんどん生まれていくといいと思っています。日本、そして世界に通用する「良いもの」、神戸の象徴となるような「神戸ブランド」を作っていけると、さらに「いい回転」が生まれていくと考えています。
―――農業振興が進むことで、「神戸ブランド」の形成にもつながっていく、ということですね。広がりがありますね。農業以外の商業についての展望を、もう少しお聞かせください。
(坊)はい。「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」周辺は、人が集まる場所になりましたから、商売をやりたい、という人がもっとたくさん来てくれたらいいですね。おしゃれなお店も増えてきています。お店が増えれば、住みたいと思う人もさらに増えますね。そうして、お店や人口が増えれば、町全体の雰囲気が変わります。そして、経済が活性化していけば、まちなみに投資できるようになるんです。もともと自然豊かなエリアですから、まちなみを整えていくことで、住む人、来る人を癒やしてくれる、「ヒーリング・ガーデン」とでも呼べるような街になっていったらいいと思っています。
―――「ヒーリング・ガーデン」。素敵ですね!確かに、こんなに自然豊かでありながら、快適に暮らすことのできる環境も整ったまちは、なかなかありませんね。
(坊)そうなんですよ。自然豊かな環境でありながら、コンビニも病院も教育機関もある。光ファイバーをはじめとする通信環境も整備されている。神戸にも大阪にも30分で出ることができる。こんなぜいたくな環境、日本中見渡しても、なかなかないですよ(笑)。

神戸に広がる、「道の駅」の成功モデル
―――最後に、 「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」の成功事例(モデルケース)をふまえて、神戸市全体のこれからの展望について、思いをお聞かせください。
(坊)はい。「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」のような取り組みの「積み重ね」が、「神戸市に対する信頼」になっていくんだと思っているんです。常に、時代に合わせて、「いい環境を作り続けていく」のをやめないことです。何かひとつ作って終わりじゃないんです。そうして、「神戸というのは、どんな時代でも生きていけるまちなんだ」「神戸というのは、時代が変わっても、誰が来ても、生きていけるまちなんだ」と思ってもらえるようになることで、「神戸市に対する信頼」が築かれるんだと思うのです。日本全体で、人口は減っていきます。じゃあ、神戸はどうしたらいいのか?「いい環境をつくる」ことですよ。「神戸ならできる!」と思ってもらって、神戸に来てもらいたいですね。
―――「変革を断行する」「いい環境を作り続ける」ということが、神戸市に対する信頼につながっていく、ということですね。それによって、神戸に来てくれる人が増えていくことで、ますます好循環が生まれていきそうです。「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」に関連した具体的な展望としてはどのようなものが考えられるでしょうか?
(坊)まず、「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」に隣接して「北神戸ゴルフ場」の広大な土地があります。もっともっと有効に使えるはずです。そして、「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」の成功例を、西区、垂水区、須磨区のほうにも展開していけたらいいと考えています。道の駅で神戸一周できるゴールデンルートを作れたらいいですね。
―――そうした構想を実現していくためには、どのようなステップが必要そうでしょうか?
(坊)地元の理解と、行政の努力が必要です。なにより、地元のことは地元が主体となって動かなくてはなりません。そして、地域の中で「やろう」という機運を作っていくために、まずは、政治家がリーダーシップをとっていかなくてはなりません。そして、地元が「やる」となったら、それを、行政は、支えていかなければなりません。その繰り返しで、神戸はどんどんいいまちになっていきますよ。